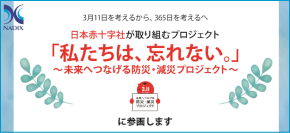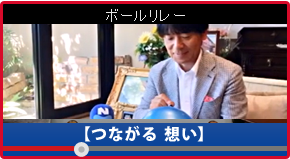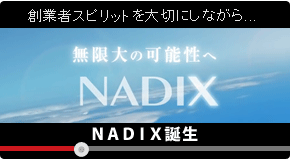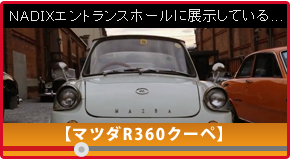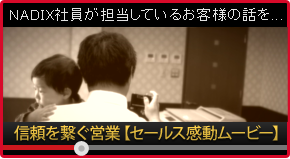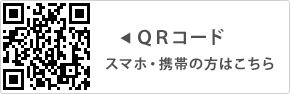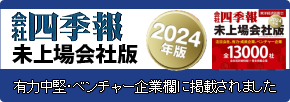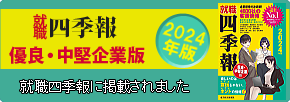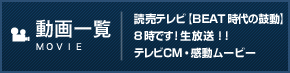がんがら火祭り
2025年08月29日 [スタッフ]
こんにちは、ナカムラシステムサービス株式会社の土井(康)でございます。
今年もお盆休みが明け、きびしい残暑が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?
1年ぶりの投稿となります。
今年も池田の伝統行事・がんがら火祭りが例年どおり8月24日に開催されました。
今では、北摂地域や大阪府を代表する火祭りになっています。
徳川三代将軍・家光の治世の正保元年(1644)、多田屋・板屋・中村屋・丸屋の4人が五月山の山上で火を灯したところ、「池田の地に愛宕(火の神)が飛来した」と評判になり、多くの人が山に押し寄せたことが起源だと伝えられています。
「がんがら火」は愛称(通称)で、本来は、城山町の人たちによる「愛宕(あたご)火」のことです。
「がんがら火」という愛称は、市内を練り歩くときに鳴らされる、鉦の音から来ているといわれています。
「家内安全」と「火難厄除け」を願って行われる「がんがら火祭り」は、平成22年1月に「池田五月山の愛宕火(がんがら火)」として、「大阪府指定無形民俗文化財」の指定を受けました。
松明の1本の長さは、約4メートル、重さ約100キログラムで、青竹を中心(芯)に肥松の木片を縄でくくりつけて作られています。
材料となる肥松は、1年前から予約し、本番の約2ヵ月前から準備にかかるそうです。
はじめに、小松明で秀望台(五月山展望台)の南斜面にある「大一」に火を灯します。
その後小松明は山を下り、綾羽2丁目の「油かけ地蔵」横の四つ辻で、大松明に火が移されます。(※巡行ルートは年により変更になる場合があるそうです)
2本1組で「人」の文字に組んだ2基の大松明が、八丁鉦や半鐘の音に合わせて、市内を勇壮に練り歩きます。
1組の大松明に15~20人がかかり、火の粉をふせぐ人、松明を支える刺股(さすまた)持ち、半鐘、御幣持ち、世話役などを含めると総勢100人にもなります。
松明から火を移しとり、家の神仏の灯明にする風習は、今も受け継がれています。
地元の氏子である城山町の人たちが、秀望台下の斜面に午後7時30分ごろ点火し、その火は約60分間燃え続けます。猪名川の川面に映る「大一」文字は何ともいえない風情があります。
昔は串し燈籠をともした「一」の文字でしたが、明治の終わりごろ、「大一」になったといわれています。
五月山の東方斜面(大明ヶ原)では、建石町の人たちによって「大」の字が灯されます。
京都の愛宕神社のご神火を「星の宮」にまつり、その火で「大一文字」とほぼ同じころ「大文字」に点火されます。
「星の宮」には「その昔、中国から渡来した呉織姫(くれはとり)、穴織姫(あやはとり)というふたりの織姫が、灯もつけず夜遅く機を織っていたところ、七つの星が降りてきてあたりを明るくした」という伝説が残っています。
そんなロマンを秘めた「星の宮」に、点火後の火を納めるため、こどもたちが竹筒に灯油を入れた松明を手に、八丁鉦を嗚らしながら下山します。
地元では「大文字献灯」と呼ばれ、親しまれています。
今年は直前に雷雨があり、小雨が降っていましたが何とか決行されたようです。
来年も開催を楽しみにしております。